海外のインター校で過ごす3年目、
高校も後半戦に入った娘が面白い課題に日々取り組んでいます。
英語、社会、音楽など科目は様々。
形式も、数週間かけて作成するレポートから、短時間で書き上げる作文、
あるいは口頭での短い発表、さらには実演など。
娘はいつもPCの画面と睨めっこしながら、あーだこーだ言いながら何やらやっています。
教科書や参考書を広げて暗記をしたり、ひたすら問題を解いて覚えたり、といった馴染みのある勉強風景とは全く違います。
彼女が取り組んでいるのは、
自分で必要な資料を調べ、考える
という勉強方法
すごくいい!
こういう勉強がさせたくて、海外に連れて来たんだ!
と心の中でバンザイしています🙌。
正解のない問い

毎回面白い課題が出される度に、
(おそらくは途方に暮れている)娘が、こんな宿題が出た〜、と言いに来ます。
待ってました!と一緒にあれこれ話をします。
私も知識と頭をフル回転させて
ヒントになりそうな事をたくさん伝え、娘をフォローします。
勿論、最終的に考えをまとめて成果物にするのは娘自身です。
私はあくまでもヒントを与えるだけ。
たくさんのヒントと、それをめぐって議論すること、それこそが最初の大切な学びだと思って一緒に楽しんでいます。
例1)英雄の評価について

これは外国語としての英語を学ぶクラスでの宿題。
何か賛否の分かれる事柄について論じよという宿題でした。
思いついたのは、桃太郎の話。
桃太郎は人間にとっては英雄だけれど、成敗された鬼の側から見たらどうだろう?
以前、家族を殺された鬼の子が泣いている大きな新聞広告が出たことがあったっけ?
立場が違えば評価も違うよね、という話になり、
悪い行いの良し悪しの判断って、どうやってするの?
から倫理の話に発展。
さらにはナポレオン、ってどう?と話が進み、
そもそもナポレオンって?となり、
歴史の勉強のやり直しにも繋がりました。

英語の授業の宿題だけど、完全に英語の勉強の枠を超えてる(^^)
例2)気になる社会問題を選んで論じる
文化や社会について学ぶ授業での課題。
社会における課題を一つ選び、調べて論じるというもの。
どこの地域のどんな課題でもいいというので、まず自分のテーマを見つけるところから大変だったようです。
教室に集っているのは、世界各地から集まって来た先生と生徒達です。
提案した課題について、必ずしも日本人の娘と同じような問題意識を持っているとは限らず、
その点でもかなり勉強になったようです。
最終的に娘が選んだのはヤングケアラーの問題でした。
日本の状況、そして他国ではどんな状況なのか?
そもそも何故それが問題なのか?
子どもの権利とは?教育とは?ケア労働って?ジェンダーの問題?と話は膨らみます。

例3)作曲してみる
音楽の課題は作曲でした。
何をテーマに、どんな曲を作りたいか、から始まります。
創作です。
今はPCで簡単にできる作曲のアプリがあるので、楽器が演奏できなくても、五線譜を手で書けなくてもオーケストラの楽譜が作れてしまうのですね。
とはいえ、曲の雰囲気も、メロディーを決めるのも、楽譜の知識なしには作れません。
音の組み合わせをあれこれ試し、拍子を計算して思い通りの形にするのは、
なかなか骨の折れる作業だったようです。
かつて習ったピアノの楽譜を引っ張り出してきて記号を確認したり、
小節の区切りの中に音符を並べるための計算をしたり、
短調と長調の違いを考えたりと今までの音楽の知識を総動員して頑張っていました。

中学の音楽で音符だの休符だの暗記した知識がやっと役に立った(^^)
考える勉強
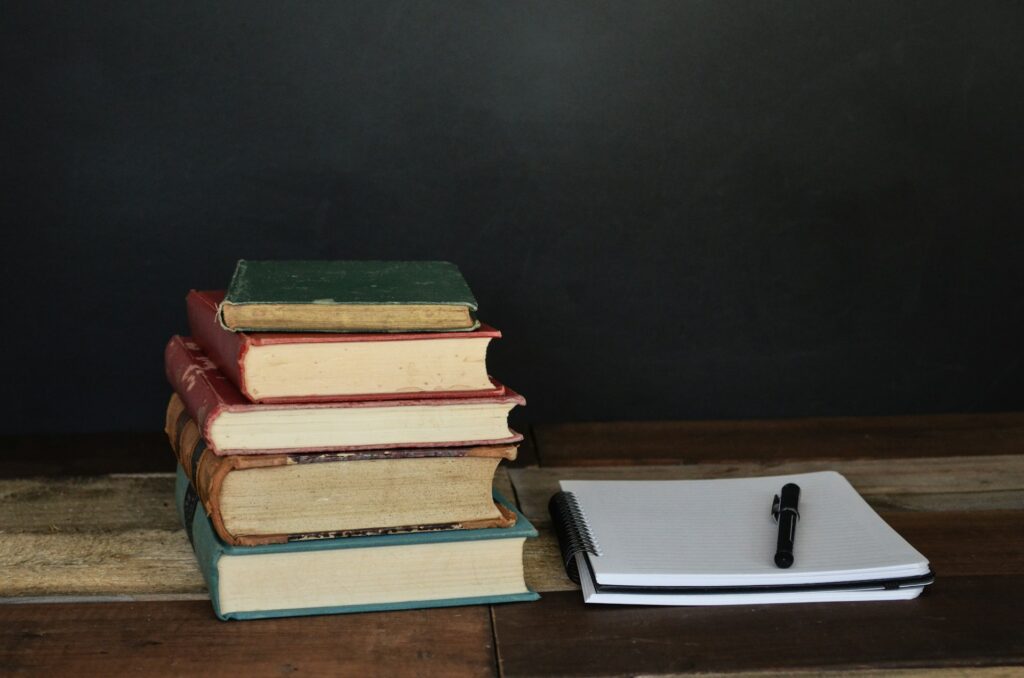
ここに紹介した、インターナショナルスクールで娘が取り組んでいる課題は
いずれも、いわゆる正解のない問いです。
人によって解が違うことについて、
自分はこう思う、と論じるためには、
根拠となる考えが必要です。
その為には納得行くまでの調査と研究が必要です。
様々な事例を調べ、考えて自分なりの解を導き出します。
もちろん、数学のように正解が一つしかない問いも解く面白さはありますし、
歴史的科学的事実として蓄積されてきた知見を理解して自分のものとする事も大切です。
そういった方面の勉強も疎かにすべきではありません。
最低限の常識を身につける必要もあるでしょう。
でも、どうでしょう?
現在は資料が手軽にスマホでいつでも参照できます。
歴史的事実や公式といった動かない知識を頑張って頭の中に蓄積する事よりも、
それらをいかに活かすか、
つまり、考える力を養う事、の方が
これからの時代は大切なんじゃないかと思うのです。

いい勉強になってるね!娘!



コメント